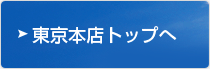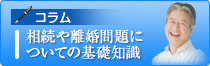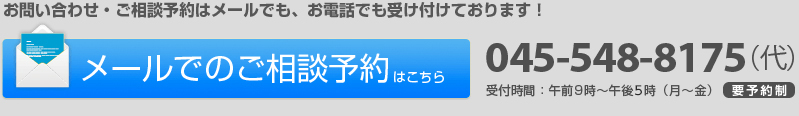TOP > 相続問題の基礎知識 > 年金の貰い過ぎ分の相続について
受け取った年金の額が正当な金額より多すぎるときは、
過去に遡って返納する義務が生じます。
死亡届を故意に出さなかった場合など、明らかに悪質なケースは当然と言えますが、
うっかりミスで手続きを怠ったときでも、返還義務がなくなることはありません。
たとえば生計を共にする配偶者が障害年金の受給者になったとき、
加給年金の支給は停止されますが、
その届出を怠っていると障害年金と加給年金を二重に受給することになり、
後に発覚すれば返還を請求されます。
なお障害年金に限らず、配偶者が厚生年金や共済年金に一定期間加入していると、
加給年金は受給できないので注意が必要です。
いずれにせよ老齢年金や障害年金を貰いすぎた場合には、
日本年金機構から返還を請求されることになりますが、
この義務は本人が死亡した後は、相続人に引き継がれることになります。
年金の過払いが後から発覚することもあるため、
相続するときには注意して調べなければなりません。
相続は資産も負債も一緒に引き継ぐことですから、負債の一種である過払い年金もまた、
当然に相続人が返還しなければなりません。
どうしても返還できない場合には相続放棄という手段もありますが、
これは死亡後3か月以内に裁判所へ申し立てなければなりません。
過払いの発覚が遅れると間に合わないこともあります。
また過払い年金の原因のほとんどは受給者の手続きの遅れですが、
年金機構の事務処理のミスも決して少ないとは言えず、
このようなケースがたびたび問題になっています。
支給された年金を使い切ってしまい、返す当てがない場合には、
民法703条の解釈を根拠にして、返還しなくてよいとする見解もあります。
しかし現状では返納請求が来るため、無視しているわけにはいきません。
ともかく年金の貰いすぎが判明した場合は、返還義務を知っておかねばなりませんし、
貰いすぎかどうか不明な場合でも、相続人は十分に注意を払う必要があります。
- 相続問題の相談は経験豊富な弁護士に
- 兄弟で揉めやすい相続問題
- 相続問題が調停へと発展した場合
- 相続税を抑える生前贈与のメリット
- 遺留分トラブルを解決する減殺請求
- 分割が難しい不動産の相続
- 遺言の作り方
- 法定相続人とは
- 遺産分割とは
- 相続税の配偶者控除とは
- 相続税の基礎控除縮小の概要
- 相続税の申告には期限がある
- 相続における遺言の力
- 相続の際の成年後見者制度とは?
- 相続の際のプラスの財産・マイナスの財産
- 相続した売れない土地の処分方法
- 相続における遺産分割協議書って
- 相続登記の委任状について
- 孤独死した父の相続放棄
- 相続放棄をするべきでしょうか?
- 祖父の前に亡くなった祖母の再相続手続きについて
- 生活保護を受給していた母の相続放棄
- 相続での通帳の取得について
- 遺産相続の分割協議について
- 相続を譲渡した場合の請求について
- 相続人からの返済要求
- 相続放棄について
- 相続の欠格について
- 年金の貰い過ぎ分の相続について
- 遺言があった場合の相続と遺留分について
- 相続放棄をする前提での車の処分について。
- 相続税について
- 相続放棄後の保険金受取について
- 離婚した夫から子供への相続について
- 相続財産管理人の選任申立
- 異母兄弟への遺産相続について
- 相続時の不動産に対する抵当権(借地権)の評価減について
- 相続した土地の木を切りたい
- 共同相続人の占有による時効取得
- 宗教法人の財産の相続について
- 遺産相続の請求について
- 認知症の祖母の相続について
- 遺産相続の時効
- 土地の相続について
- 法定相続人と受遺者の役割分担
- 被相続人の預金の使い込みに対する不当利得返還請求
- 法定相続分について
- 子供への遺産相続について
- 不動産の相続登記について
- 相続放棄後の手続き
- マンションの相続について
- 想像もできないほどかかっている?相続税の秘密
- 知っておきたい相続税対策
- 法定相続人と相続分について
- 相続財産でも相続税がかかるものについて
- 相続税の税率について
- 相続税のかからない非課税財産について
- みなし相続財産は相続税の対象になる?
- 収めた相続税が還付されるケースとは
- 相続人が複数の場合に用いる按分割合とは?
- 車を相続する場合の相続税とは?
- 有価証券の相続税とは?
- 株式と相続税について
- 太陽光発電を用いた相続税対策とは
- 相続税と住宅ローンの関係について
- 相続税は宝石などのジュエリーも対象となるのか
- 相続税を節税する方法とは
- 養子縁組を利用した相続税対策について
- 生命保険を利用した相続税対策について
- 海外移住している場合の相続税
- 店舗兼住宅の相続税はどうなるのか
- 孫に遺産を相続させたい時の相続税
- 相続税が払えない場合について
- 二世帯住宅を活用した相続税対策とは
- 相続税の「更正の請求」とは
- 相続税の申告に間違えた場合は修正申告
- 代償分割における相続税とは
- 法人化で相続税を節税する
- タワーマンションの相続税を節税する
- アパートを建築する際の相続税対策
- 空き家の相続税とは
- 確定申告の際に相続税はどうなるのか
- 更地にかかる相続税問題とは
- 貸家建付地の相続税とは
- 内縁の妻の相続税を知ろう
- 牛馬等の相続税とは
- 連れ子で再婚した際の相続税
- 相続税の計算方法について
- 相続税を申告漏れした場合は?
- 無道路地の相続税とは
- 相続税における物納とは
- 未収家賃は相続税がかかるのか
- 特別縁故者の相続税について
- 縄伸びしている場合の相続税とは
- 骨董品の相続税について
- 遺族年金にかかる相続税とは
- 相続税における申告義務とは
- 相続税が対象外になる財産とは
- 税制改正による相続税の変更点とは
- 相続税対策の有効な開始時期とは
- 相続税対策における事前対策と事後対策について
- 相続税の対象になるものとは